注目の研究
現在注目されている研究をご紹介します。

ダイヤモンド半導体 関連研究
宇宙で利用できるデバイス開発
ダイヤモンドを使った究極のパワー半導体
次世代の究極のパワー半導体であるダイヤモンド半導体デバイスを作製し、世界最高の出力電圧、電力の記録を更新。ダイヤモンド半導体は、従来のシリコン等と比べ、放熱性、耐放射線性等に優れ宇宙空間でも安定した動作が期待できます。宇宙空間の人工衛星を基地局とした高速無線通信が現実味を帯びてくる中で、人工衛星で使われている真空管に代わる高出力、高周波数の半導体デバイスとして、実用化が急がれています。令和5年度からはJAXA宇宙科学研究所等と文部科学省「宇宙開発利用加速化戦略プログラム」において「ダイヤモンド半導体デバイスの宇宙通信向けマイクロ波電力増幅デバイスの開発」を進めています。
【研究代表者】 理工学系 嘉数 誠 教授

アトピー性皮膚炎 関連研究
アトピー性皮膚炎の痒みの原因の探求から
新たな治療薬の開発へ
出原教授ら研究グループは数年前に炎症や痒み症状を示すアトピー性皮膚炎モデルマウスを開発し、その痒みの原因の探究を可能としました。その後、アトピー性皮膚炎患者の皮膚組織で作られるペリオスチンが、知覚神経に作用して痒みを引き起こすとともに、その阻害剤が痒みや炎症を軽減することを発見。この発見により、アトピー性皮膚炎の治療薬の開発が大きく進むものと期待されています。令和5年に行った「アトピー性皮膚炎|痒みの仕組みの解明と、治療薬の開発研究」のクラウドファンディングでは約1,000名の方の支援を受け研究を進めています。
【研究代表者】 医学系 出原 賢治 教授
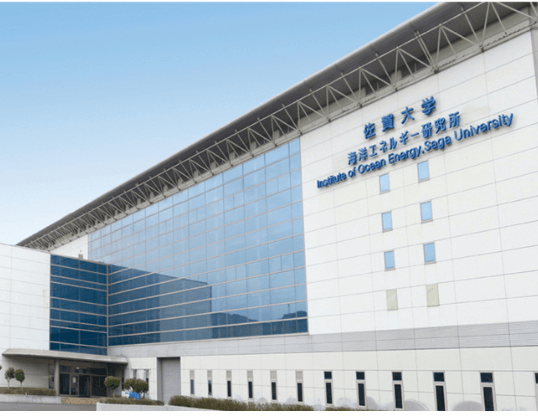
海洋エネルギー 関連研究
海洋エネルギーの国際的な研究拠点・知の世界展開
世界を牽引する技術と人材がここに
海洋エネルギー研究所は、海洋エネルギーに関する研究教育及び科学技術を戦略的に推進する国際的な先導的中核研究拠点です。令和5年度には、海洋エネルギーの未来を切り開く研究成果と人材育成で世界を牽引した功績が認められ、第15回海洋立国推進功労者内閣総理大臣表彰を受賞しました。令和4年度には、環境省の「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」に採択され、企業と共同して海洋深層水を活用した海洋温度差発電(OTEC)の商用化に向けた実証事業に取り組んでいます。本事業ではOTEC商用化に向け海水からの大規模熱回収技術の確立を目指します。
【研究代表者】 海洋エネルギー研究所 池上 康之 所長・教授

プラントベースフード(PBF)関連研究
CO2を利用して効率よく大豆を育成
プロテインクライシスの解決へ
渡邊准教授の研究グループは、伊藤忠エネクス株式会社、不二製油グループ本社株式会社、大和ハウス工業株式会社と共同で、佐賀市の清掃工業から排出される二酸化炭素(CO2)を利用し、貴重なたんぱく源である大豆の効率的な生産により、プラントベースフード(Plant based food:PBF)※の利用拡大を目指す研究プロジェクトを産学官連携により進めています。世界的な社会問題であるタンパク質の供給不足(プロテインクライシス)の解決が期待されます。
※PBFとは、植物性原料で動物性食品を再現する次世代食です。
【研究代表者】 農学部 渡邊 啓史 准教授

ウエラブル皮膚ガスセンサー関連研究
薄膜フィルムセンサーで生体ガスを測定
皮膚に貼るだけで健康管理ができる時代に
冨永教授の研究グループは、従来の半導体ガスセンサーに比べて「ガスの選択性」と「感度」に優れた酵素修飾型の皮膚ガスセンサーの研究を進めています。薄膜フィルムからなるセンサー(酵素薄膜センサー)はウェアラブル性が極めて高く、スマートウォッチに内蔵できる超小型測定デバイスの開発が可能です。既に皮膚からのアルコールガス、アセトアルデヒドガスの連続測定に成功しています。今後適切な酵素を用いることで、個人の健康管理に有用な生体ガスの多種類同時検出や、特異的で高感度な環境センサー等への応用が期待されます。
【研究代表者】 理工学部 冨永 昌人 教授
研究に関連する最新のNews&Topics
JST 大学発新産業創出基金事業への研究提案が2件採択
本学教員の共同研究成果が日本油化学会でポスター賞受賞
「WasteManegement誌」への投稿論文掲載
JST新技術説明会に本学教員が登壇
「SAGA TSUNAGI コンベンション」に本学教員が出展
本学の研究に関するお問い合わせ
担当窓口
リージョナル・イノベーションセンター URAチーム
〒840-8502 佐賀市本庄町1番地
TEL. 0952-28-8961
E-Mail:suric★ml.cc.saga-u.ac.jp(★を@に変換してください)
